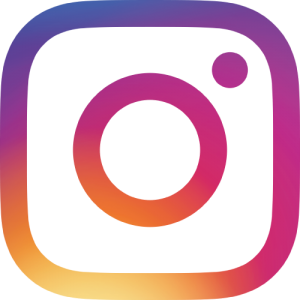学習利用のご案内(団体向け)
日本モンキーセンターは、博物館活動の一環として教育活動にも力を入れています。
幼稚園から大学生や教員まで、また学校団体から子ども会やスポーツクラブまで、学習目的に応じてレクチャー、スポットガイド、体験活動などさまざまな教育プログラムを用意しています。
学びの場として、ぜひご活用ください。
■学習利用の手引きと申込書等
必ず学習利用の手引きをご覧ください。
 学習利用の手引き(2024年7月改訂)
学習利用の手引き(2024年7月改訂)
内容
・園内での注意事項
・事前事後学習のススメ
・各種教育プログラム紹介
・活動の流れ
・申込方法、申込・お問合わせ先
 団体利用 申込書(2023年3月改訂)
団体利用 申込書(2023年3月改訂)
団体利用する場合の申込書です。教育プログラムも利用する場合は、必ず学校教員等指導者の方ご自身がご記入ください。
申込方法:
1)お電話にて日程や学習内容などをご相談ください。
2)教育プログラムを利用する場合は、なるべく下見にお越しください。キュレーターやエデュケーターと打ち合わせをおこないます。
3)この申込書にご記入の上、FAXにてお送りください。
 減免申請書(2024年4月改訂)
減免申請書(2024年4月改訂)
障がい者手帳をお持ちの方と介助者1名は、障がい者手帳の提示により入園料が半額になります。団体入園の場合はこの減免申請書を団体代表者名にて事前にご提出いただくことで、手帳提示が免除されます。
記入捺印済みの申請書を事前にFAXのうえ、原本は来園当日にお持ちください。
■学習利用の手引きに関する補足情報
学習利用の手引きに掲載されている施設や教材等に関する補足情報です。
□施設に関する補足資料
□教材キット「くらべてみよう、サルとキミ」
□紙芝居「日本モンキーセンターってどんなところ?」

小学校低学年向けの事前学習用の紙芝居です。
日本モンキーセンターの概要や観察のポイントを紹介しています。
2023年度博物館実習生が制作しました。
【⇒紙芝居本体へ】
□ワークシート「霊長類の行動観察入門」

行動観察とは、ヒトを含め動物の行動を科学的・定量的に評価するための手法です。このワークシートでは、1個体に注目して観察する「個体追跡法」と、一定時間間隔で行動を記録する「瞬間記録法」を使って行動観察を体験します。最後に観察個体ごと、種ごとにまとめをし比較をすることで、同じ霊長類であっても行動や社会に多様性があることに、自ら気づくことができます。また科学的なデータの取り扱いを体験することができます。
【⇒詳細ページへ】●公開時リンク先変更
□ワークシート「サルの体のつくりと動きを調べよう」

園内でサルをじっくり観察するためのワークシートです。
大きさや形の異なる4種類のサルを観察し、体のつくりの違いと動物の移動の仕方(ロコモーション)との関係を調べます。また、生息環境や食性についての情報を加えることで、動物の形態と生息環境との密接な関係を学ぶことができます。
【⇒詳細ページへ】●公開時リンク先変更
□ワークシート「遠くて近い!サルと私たちのくらし」

来園前の事前学習用のワークシートです。
身近なものの原産国しらべ、霊長類の生息地しらべをおこない、私たちのくらしと、霊長類たちのすむ環境について考えます。
【⇒詳細ページへ】●公開時リンク先変更
□「霊長類図鑑 サルを知ることはヒトを知ること」
学習教材としてもオススメです。一例として、小中学校の動物を取り扱う単元での活用が考えられます。ヒトと共通性の高いサル類を題材にすることで、実際に自分と比較しながら効果的に学習できます。サル類と自分の違いやサルたちの種ごとの違いを考えることで、種の多様性にも目を向け、差異に注目することで進化についても学習の幅を広げていくことができます。校外学習の事前、事後学習の補助教材としても最適です。
A判変形 156ページ
価格:1,600円+税
(園内ミュージアムショップでは特別価格で税込1,600円)
ISBN:978-4-903473-51-1
各種通販サイト他、出版社のサイトからも購入できます。
【⇒京都通信社の「霊長類図鑑」のページへ】
【⇒Amazonの「霊長類図鑑」の販売ページへ】
※この紹介文は2019年度博物館実習生が作成しました。
□高校生による探究活動
| 探究活動の例 | 参照URL |
| ボリビアリスザルのアカンボウに対する接触について1年間の個体追跡をおこなった例 | https://doi.org/10.14907/primate.34.0_79_2 |
| ワオキツネザルの活動の変化を季節が変わるごとに来園して調査した例 | https://www.jst.go.jp/cpse/jissen/about/report.html |

専門の学芸員が在籍しています。探究活動のテーマ決めや探究方法の検討などの段階から相談していただけます。必要があればオリジナルのプログラムを組み、学芸員と学校の教員との連携により探究の質を高められます。
約60種もの飼育動物や1万2千点ほどの標本を所蔵しています。生年月日や家系が記録された生きた動物たちや、豊富な標本の活用を検討できます。例えば、体の動きを考える場合、骨格標本と生きた動物の観察を組み合わせて、より深い理解をすることができます。
【日本モンキーセンター Web霊長類図鑑】
【飼育霊長類標本データベース(CaPriCo)】

日本モンキーセンターの主催するプリマーテス研究会では大学の研究者に混ざって高校生たちが口頭発表やポスター発表をおこなっています。また、日本霊長類学会では中高生がポスター発表をする時間が設けられています。過去には優秀賞を受賞した例もあります。
■犬山市の小中学校と連携して開拓した学び

これまで日本モンキーセンターは犬山市の小中学校と理科副教本「理科だいすき」の作成を通して、様々な教材開発をしてきました。また、1日モンキーデーといった独自の取り組みや遠足、アウトリーチ(出前授業)など、連携して学びを開拓してきました。最初の取り組みから15年の積み上げにより、多くの教材・資料を世に送り出しています。これらを多くの小・中学校や教育機関に活用してもらうために、YouTube教材・3D骨格標本・配布教材として閲覧できるようにしました。ぜひご活用ください。
【⇒「犬山市の小中学校と連携して開拓した学び」のページへ】
■博学連携等に関する研究発表
日本モンキーセンターでは、動物園における先進的な教育活動に取り組んでいます。
研究成果は論文や研究発表として発信しています。
□印刷物
| 高野智, 赤見理恵.2019. | |||
| 動物園が小学校に ~全学年が取り組む「1日モンキーデー」の試み~. | |||
| 日本科学教育学会研究会研究報告. 33(8): 89-92. | |||
| 赤見理恵, 高野智, 江藤彩子, 小比賀正規.2018. | |||
| 貸出用事前学習教材の開発~博学連携の裾野を広げるために~. | |||
| 日本動物園水族館教育研究会誌. 25: 27-36. | |||
| 荒木謙太, 鏡味芳宏, 赤見理恵, 堀込亮意, 木村直人, 伊谷原一.2015. | |||
| 動物福祉に配慮したふれあい方法と展示の改善. | |||
| 日本動物園水族館教育研究会誌. 22: 5-8. | |||
| 赤見理恵, 高野智, 南曜子.2015. | |||
| 自由連想調査による学習効果の定性的評価の試み. | |||
| 日本動物園水族館教育研究会誌. 22: 73-78. | |||
| 赤見理恵.2015. | |||
| 第31回日本霊長類学会大会記 自由集会-6 野生への窓を開く動物園教育. | |||
| 霊長類研究. 31: 160-162. | |||
| 高野智.2014. | |||
| 自然人類学の要素を取り入れた博学連携プログラム. | |||
| Anthropological Science (Japanese Series) 122: 68-70. | |||
| 安田知夏,荒木謙太,高野智,阿部菜穂美,岩田真菜美.2011. | |||
| ふれあい施設KIDSZOOにおける学習プログラムの開発と実践. | |||
| 日本動物園水族館教育研究会誌2012年号: 38-40. | |||
| 高野 智. 2010. | |||
| 日本モンキーセンターの生物多様性教育 ―複雑なものを複雑なままに―. | |||
| 日本科学教育学会年会論文集34:217-218. | |||
| 古市博之,高野 智,赤見理恵,阿部晴恵,夏目明香. 2009. | |||
| カリキュラムの中で動物園を生かすには -日本モンキーセンターとの連携事例. | |||
| 日本動物園水族館教育研究会誌2009年号: 12-15. | |||
| 高野 智. 2008. | |||
| 日本モンキーセンターにおける教員向け研修会 ―研修会の先に見えているもの―. | |||
| 日本科学教育学会第32回年会論文集:391-392. | |||
| 赤見理恵,高野智,阿部晴恵,夏目明香, 河村雅之, 高瀬雄矢, 古市博之. 2009. | |||
| 地域の子どもたちの成長とともに~地域の学校との継続的な連携事例~. | |||
| 日本動物園水族館教育研究会誌2009年号: 16-21. | |||
| 高野 智. 2007. | |||
| サルを知り、ヒトを知る 日本モンキーセンター. | |||
| 理科教室2007年8月号(50巻第8号):76-80. | |||
□学会・研究会
| 高野智, 古市博之, 高木一樹, 赤見理恵. 2019. | |||
| 生体と標本の観察から学ぶ動物の体のつくりと運動 ―愛知県犬山市小学校4年生「モンキーワーク」の実践―. | |||
| 日本生物教育学会第103回全国大会. (愛知県) | |||
| 高野智. 2015. | |||
| 日本モンキーセンターにおける地域の学校との連携:10年間の歩み. | |||
| 第56回日本動物園水族館教育研究会. (沖縄県) | |||
| 高野智. 2015. | |||
| 日本モンキーセンターの生息地研修とその展開. | |||
| 第31回日本霊長類学会大会自由集会「野生への窓を開く動物園教育」. (京都府) | |||
| 坂口真悟, 荒木謙太, 石田崇斗, 大島悠輝. 2015. | |||
| 日本モンキーセンターにおける霊長類のより深い理解を目的とした体験型イベントの取り組み. | |||
| 動物園大学6 in 犬山 ず~だなも。(愛知県) | |||
| 石田崇斗, 坂口真悟, 鏡味芳宏, 荒木謙太, 綿貫宏史朗, 新宅勇太, 赤見理恵. 2015. | |||
| JMCにおけるエンリッチメント体験を通した教育活動. | |||
| 第110回日本動物園水族館協会中部ブロック飼育技術者研修会. (静岡県) | |||
| 荒木謙太, 山田将也, 赤見理恵, 木村直人, 伊谷原一. 2015. | |||
| 学ぶ!観る!リスザルのおやつ作り体験. | |||
| 第56回日本動物園水族館教育研究会. (沖縄県) | |||
| 赤見理恵. 2015. | |||
| 学校貸出用事前学習教材の開発~博学連携の裾野を広げるために~. | |||
| 第56回日本動物園水族館教育研究会. (沖縄県) | |||
| 赤見理恵. 2015. | |||
| 霊長類から学ぶ小学5年生理科「人のたんじょう」. | |||
| 第18回SAGAシンポジウム. (京都府) | |||
| 荒木謙太, 鏡味芳宏, 赤見理恵, 堀込亮意, 木村直人, 伊谷原一. 2014. | |||
| 動物福祉に配慮したふれあい方法と展示の改善. | |||
| 第55回日本動物園水族館教育研究会.(宮城県) | |||
| 赤見理恵, 高野智, 南曜子. 2014. | |||
| 自由連想調査による学習効果の定性的評価の試み. | |||
| 第55回日本動物園水族館教育研究会.(宮城県) | |||
| 高野智, 赤見理恵, 木村直人. 2014. | |||
| 動物園が企画する教員向け研修会. | |||
| 日本科学教育学会第38回年会. (埼玉県) | |||
| Akami R, Takano T, Eto A. 2014. | |||
| Educational programs and evaluation systems in JMC. | |||
| The 22nd Conference of International Zoo Educators Association. (Hong Kong, China) | |||
| 高野智、赤見理恵. 2014. | |||
| 学校教育における霊長類の教材化 ~日本モンキーセンターにおける博学連携~. | |||
| 第30回日本霊長類学会大会(大阪府) | |||
| 古市博之、高野智、赤見理恵、勝見乃里江. 2013. | |||
| 連携が根付いていくために~物・対話・信頼、そして継続~. | |||
| 第53回日本動物園水族館教育研究会(犬山) | |||
| 神田恵、江藤彩子、赤見理恵、高野智. 2013. | |||
| 『いつも楽しい動物園』になるためには何が必要か?~団体の継続利用をアンケートから考える~. | |||
| 第53回日本動物園水族館教育研究会(犬山) | |||
| 高野智. 2012. | |||
| 自然人類学の要素を取り入れた博学連携プログラム. | |||
| 第66回日本人類学会大会. (神奈川) | |||
| 赤見理恵,高野智,江藤彩子,神田恵,小島省,南曜子.2011. | |||
| 教員養成課程の学生を対象とした行動観察実習の事例. | |||
| 第52回日本動物園水族館教育研究会(神奈川) | |||
| 安田知夏,荒木謙太,高野智,阿部菜穂美,岩田真菜美.2011. | |||
| ふれあい施設KIDSZOOにおける学習プログラムの開発と実践. | |||
| 第52回日本動物園水族館教育研究会(神奈川) | |||
| 赤見理恵,高野 智,江藤彩子,神田 恵. 2010. | |||
| 楽しく学ぶための評価と改善 ~3つの指標で実施したレクチャーの評価~. | |||
| 第51回日本動物園水族館教育研究会(北九州) | |||
| 高野 智,赤見理恵. 2010. | |||
| 学術標本を活用した学習プログラムの開発と実践. | |||
| 第58回動物園技術者研究会(神戸) | |||
| 高野 智. 2010. | |||
| 日本モンキーセンターの生物多様性教育 ―複雑なものを複雑なままに―. | |||
| 日本科学教育学会第34回年会(広島) | |||
| 高野 智,赤見理恵. 2009. | |||
| 子供とのコミュニケーションは教師とのコミュニケーションから -日本モンキーセンターにおける博学連携の深め方-. | |||
| 第50回日本動物園水族館教育研究会(大洗) | |||
| 古市博之,高野 智,赤見理恵. 2009. | |||
| 進化の授業を創造する 日本モンキーセンターとの連携. | |||
| 第50回日本動物園水族館教育研究会(大洗) | |||
| 赤見理恵,高野 智,江藤彩子,神田 恵. 2009. | |||
| 事前事後学習の実態と指導者とのコミュニケーション ~学習利用団体へのアンケートから~. | |||
| 第50回日本動物園水族館教育研究会(大洗) | |||
| 古市博之,高野 智 2009. | |||
| カリキュラムの中で動物園を生かすには ~モンキーセンターとの連携事例~. | |||
| 第49回日本動物園水族館教育研究会(横浜) | |||
| 赤見理恵,高野 智,阿部晴恵,夏目明香, 河村雅之, 高瀬雄矢, 古市博之 2009. | |||
| 地域の子どもたちの成長とともに~地域の学校との継続的な連携事例~. | |||
| 第49回日本動物園水族館教育研究会(横浜) | |||
| 赤見理恵,高野 智,阿部晴恵,夏目明香 2008. | |||
| サル類の飼育展示および標本を活用した学校と博物館の連携授業の展開. | |||
| 第11回SAGAシンポジウム(東京) | |||
| 高野 智 2008. | |||
| 人類学と学校教育の接点 ~日本モンキーセンターにおける教育プログラム~. | |||
| 第62回日本人類学会大会 (名古屋) | |||
| 高野 智 2008. | |||
| 日本モンキーセンターにおける教員向け研修会 ―研修会の先に見えているもの―. | |||
| 日本科学教育学会第32回年会(岡山) | |||
2008~2010年度 基盤研究(C) 課題番号:20605014 研究代表者:高野 智
研究課題名:「学校教育との連携による地域密着型博物館活動の展開」
2013~2015年度 若手研究(B) 課題番号:25871078 研究代表者:赤見 理恵
研究課題名:「動物園における学習利用促進のための利用者研究と事前学習教材の開発」
2016~2018年度 基盤研究(C) 課題番号:16K01205 研究代表者:赤見 理恵
研究課題名:「プロトコル分析を用いた動物園における学びの構造的研究」
2019~2022年度 基盤研究(C) 課題番号:19K02721 研究代表者:赤見 理恵
研究課題名:「動物園を活用した保全教育プログラムと教材の開発と評価」
2020~2023年度 基盤研究(C) 課題番号:20K03288 研究代表者:高野 智
研究課題名:「新学習指導要領下における博物館学校連携の継続的・定量的評価の試み」
2023~2025年度 基盤研究(C) 課題番号:23K02426 研究代表者:赤見 理恵
研究課題名:「動物園と高等学校等の連携による「総合的な探究の時間」の実践」