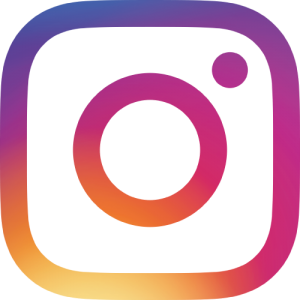モンキー日曜サロン
研究者(やその卵)に、研究内容をわかりやすく紹介していただきます。 サロン形式の堅苦しくないイベントです。 参加費無料&事前申込不要ですので、お気軽にご参加ください。
■日程:春から秋の月1~2回 日曜日 11:00~11:45 ※一部例外あり
■場所:ビジターセンター ホール
■主催:公益財団法人日本モンキーセンター、京都大学野生動物研究センター
※友の会のマイメニューをお持ちの方(サポート会員の方、クレジットカード決済で入会された一般会員の方)を対象に、 Zoomを利用したオンライン配信をおこなっています。 マイメニューの「会員特典クーポン」をご覧ください。
>>日本モンキーセンター友の会
以下は終了したモンキー日曜サロンです。
第88回モンキー日曜サロン
「毒を持つ外来種を捕食するカンムリワシの不思議 」
2025/6/29(日) 14:00~14:45 ※開催時間が通常と異なりますのでご注意ください
戸部 有紗 先生(京都大学野生動物研究センター)
沖縄県の西表島と石垣島のみに生息するカンムリワシは、絶滅危惧IA類に指定される希少な猛禽類で、現在その数はわずか200羽ほどです。島の民謡に登場するなど、地元ではとても身近な存在でもあります。 そんなカンムリワシが注目されている理由のひとつに、「毒を持つ外来種を食べる」という行動が挙げられます。1978年に石垣島に持ち込まれた外来種であるオオヒキガエルは、強い毒を分泌することで知られています。同様にこのカエルが人為的に持ち込まれたオーストラリアでは、毒によって捕食者が中毒死した例が報告されています。 なぜカンムリワシはオオヒキガエルを食べることができるのでしょうか? これまでこの謎については、科学的に詳しく調べられてきませんでした。今回の日曜サロンでは、最新の遺伝解析技術を使い、この不思議にせまった研究についてご紹介します。


第87回モンキー日曜サロン
「ニホンザルはコンタクトコールで何をどうやって伝えるのか?」
2024/12/1(日) 11:00~11:45
勝 野吏子 先生(大阪大学大学院 人間科学研究科)
サルといえば「キーキー」と鳴いているイメージがあるかもしれません。でもニホンザルをよく観察してみると、澄んだ声で「クー」と鳴いたり、静かな声で「グッグッ」と互いにやり取りしたりしています。これらの穏やかな音声はコンタクトコールと呼ばれ、集団内の個体同士で鳴き交わされます。ニホンザルはこれらの音声で、何を伝えているのでしょうか。また、相手に音声が伝わるように、何か工夫をしているのでしょうか。飼育、野生のニホンザルを対象として行われてきたこれまでの研究や、私自身が餌づけ集団のニホンザルを対象として行ってきた研究から、分かってきたことをお話しします。


第86回モンキー日曜サロン
「iPS細胞を使って探るテナガザルの腕の伸ばしかた」
2024/11/3(日) 11:00~11:45
濱嵜 裕介 先生(京都大学 ヒト行動進化研究センター)
テナガザルはその名の通り長い腕が特徴的で、日本モンキーセンターでも、テナガザルが長い腕を使って枝から枝へ飛び回る姿を見ることができます。しかし、テナガザルの長い腕はどのように進化してきたのでしょうか。私はこれを調べるためにiPS細胞を使った研究を行なっています。iPS細胞と言えば再生医療や創薬などが思い浮かびますが、実は様々な霊長類の進化の研究にも大きく役立ちます。 今回の日曜サロンでは、iPS細胞とは何か、iPS細胞がどのように霊長類の研究に役立つのか、そして、現在私がiPS細胞を使って進めている、テナガザルの長い腕の進化を探る研究についてご紹介したいと思います。

第85回モンキー日曜サロン
「化石から復元する絶滅したキツネザルの脳」
2024/10/27(日) 11:00~11:45
豊田 直人 先生(京都大学 ヒト行動進化研究センター)
ここ犬山市から遥か11,200㎞、マダガスカル島には沢山の種類のキツネザルの仲間が生息しており、その数なんと約100種類にも及びます。食べ物の好みも違えば、得意な運動の仕方も違えば、目が覚めている時間帯も違う、そんなキツネザルの仲間ですが、人間の影響などによって500年以上前に絶滅してしまったものもいます。そういった絶滅したキツネザルの仲間がどんな生き方(生態)をしていたのか、知りたくありませんか?私は、キツネザルの頭蓋骨の化石から脳のかたちを復元して、脳のどの部分が大きくなっているのかを調べることで、キツネザルの絶滅種の生態を推定しています。今回の日曜サロンでは、これまでの研究で分かったことと合わせて、研究者が普段どのように化石を研究しているか、研究者の生態もご紹介したいと思います。

ワオキツネザルの頭蓋骨(黄色)と、頭蓋骨から推定された脳のかたち(青)。頭蓋骨を前からみています。
第84回モンキー日曜サロン
「サルとヒトののどを比べて探ることばの起源」
2024/6/16(日) 11:00~11:45
西村 剛 先生(京都大学 ヒト行動進化研究センター)
私たちは、のどにある声帯を振るわせて声をつくっています。しゃべったり、うたったり、どなったりと、ときどきに応じて、声帯の振るわせ方は、異なります。サルは、種が違えば、声も違います。ニホンザルは柔らかくクーとなき、マーモセットは甲高くフィーと、サキはキャキャキャとないています。しかし、私たちのように長々としゃべり、朗々と歌ったりはしません。なぜでしょう? サルののどのかたちや声帯の振るわせ方の最新の研究から、私たちの声の特徴とその進化を紐解きます。

第83回モンキー日曜サロン
「あくびは伝染する、おしっこも伝染る?~チンパンジーの行動伝染現象~」
2024/5/26(日) 11:00~11:45
大西 絵奈 先生(京都大学 野生動物研究センター)
おしっこ、いつしたくなりますか? もちろん尿が溜まればしたくなると思います。でも本当にそれだけでしょうか。家を出る前にしたくなる、本屋に行ったらしたくなる、誰かがトイレへ行くのを見るとしたくなる・・・そんなことって、ありませんか? チンパンジーの観察中、排尿が伝染しているような場面がよく見られます。誰かが排尿して、そのあとに他の誰かが排尿する、という場面です。これまで排尿の社会的側面についての学術的な議論はほとんどありません。でももしかしたら、あくびの伝染のように、排尿も他者に伝染するのかもしれません。だとしたらなぜ? 私のおこなっているチンパンジーの排尿伝染研究についてお話しします。