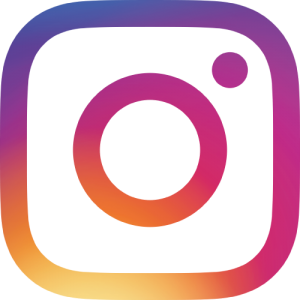2025年度 モンキーキャンパス
サルを知ることはヒトを知ること・・・
サルやヒトにまつわるさまざまな話題を通して、生物の多様性や進化について考えてみませんか?
京都大学野生動物研究センターとの共催で開催します!
【5/18】申込締切を5/25(日)に延長しました!
【4/1】募集開始しました。
【3/31】募集要綱を掲載しました。募集は4/1からです。
■募集要綱
主催:公益財団法人日本モンキーセンター
共催:京都大学野生動物研究センター
受講資格:日本モンキーセンター友の会の会員であること
⇒日本モンキーセンター友の会のページへ
募集期間:2025年4/1(火)~5/18(日) ⇒5/25(日)に延長しました!
開講日:2025年6月から11月の原則第1日曜日(講師の都合等により変動あり)
開講日のスケジュール:
10:00~10:05 講師紹介
10:05~11:30 講義
11:30~12:00 質疑応答
13:00頃~ サークル活動 ⇒サークル活動の紹介
※ 講師等の都合により若干の時間変更の場合あり
開催場所:日本モンキーセンター 世界サル類動物園内(愛知県犬山市) ビジターセンター ホール
募集人数:100名 ※定員に達し次第締め切り
受講費:12,000円(全6回分) ただし2025年4月1日時点で20才以下の方は9,000円
申込方法:KKday Japanのサイトよりお申し込みください。
※申し込み時に友の会の会員番号が必要です。入会、更新手続きはお申し込み前にお済ませください
※受講期間中に友の会の有効期限が切れ、更新手続きをされない場合は受講をお断りすることがあります。
その際の受講費の返金はいたしかねます。
※各回終了後、約1週間の見逃し配信をご覧いただけます。
■講義スケジュール ※やむを得ない事情により開催日を変更する場合があります
第1回 6/8(日)
「なぜ外来生物は防除しなくてはならないのか? ~終わりなき侵略者との闘い」
五箇公一(国立環境研究所 生物多様性領域 侵入生物研究チームリーダー)
1990 年、京都大学大学院修士課程修了。同年宇部興産株式会社入社。1996 年、博士号取得。 同年 12 月から国立環境研究所に転じ、 現在は侵入生物研究チームリーダー。専門は保全生態学、農薬科学、ダニ学。ヒアリなどの外来生物防除、化学農薬のリスク管理、新型コロナを含む人獣共通感染症対策など、生態リスク研究を通じて生物多様性と人間社会の関わり方や持続性について模索している。著書に『これからの時代を生きるための生物学入門』(辰巳出版)など。
第2回 7/6(日)
「ヒトとヒト以外の霊長類のゲノム比較から探る遺伝的多様性のメカニズム」
颯田葉子(総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター 教授)
東京都生まれ。お茶の水女子大学理学研究科修士課程修了、九州大学博士(理学)。国立遺伝学研究所、ドイツ・マックスプランク生物学研究所でのポスドク、総合研究大学院大学助教授を経て、2006年に教授。遺伝的多様性のメカニズムに興味があり、免疫や嗅覚、味覚などに関わる遺伝子の進化を研究してきた。著書に『環境を〈感じる〉』(岩波科学ライブラリー)や『肥満は進化の産物か?:遺伝子進化が病気を生み出すメカニズム』(DOJIN選書)など。
第3回 8/3(日)
「動物園との協働による絶滅危惧種の繁殖研究から生息域外保全へ」
楠田哲士(岐阜大学応用生物科学部 教授)
神戸市生まれ。岐阜大学大学院連合農学研究科博士後期課程修了、博士(農学)。岐阜大学動物園生物学研究センター長、日本動物園水族館協会生物多様性委員会外部委員。専門は動物保全繁殖学、動物園学。全国の動物園や日本動物園水族館協会、環境省などと飼育下繁殖促進にむけた繁殖生理の研究を行う。主な編著監修書に『動物園学』(文永堂出版)、『動物園学入門』(朝倉書店)、『神の鳥ライチョウの生態と保全』(緑書房)など。
第4回 9/7(日)
「古生物復元画と系統樹マンダラポスターの制作プロセス」
小田 隆(京都精華大学マンガ学部 教授)
三重県生まれ。1995年、東京藝術大学美術研究科修士課程修了。油画と壁画を専攻する。1996年に恐竜の化石の組み立てに参加したことから、復元画の制作を始める。1995年より個展、グループ展を多数開催。また、1998年から現在にいたるまで、博物館のグラフィック展示、図鑑の復元画、絵本などを多数制作してきた。幅広い古生物学者たちとの交流の中で、科学的に資料に支えられるとともに、オリジナリティに富んだ作品群を生み出し続けている。
第5回 10/5(日)
「ヒト科におけるメスの生き方の選択」
古市剛史(京都大学名誉教授)
滋賀県生まれ。京都大学理学部卒業、同理学研究科修了、博士(理学)。明治学院大学を経て2023年まで京都大学霊長類研究所教授。大学入学前に立ち寄った下北半島のニホンザルに魅せられ、サルの研究を通じたヒトの進化の解明を志す。屋久島のニホンザルの研究を経て、コンゴ民主共和国のボノボ、ウガンダのチンパンジーの研究を続ける。著書に『ビーリアの住む森で』(東京化学同人)、『あなたはボノボ、それともチンパンジー?』(朝日選書)など。
第6回 11/2(日)
「野生動物とどうつきあうか-現状とこれから」
室山泰之(東洋大学経営学部 教授)
京都府生まれ。京都大学理学研究科博士後期課程修了、京都大学博士(理学)。京都大学霊長類研究所助教授、兵庫県立大学教授を経て、2013年4 月より現職。霊長類の社会行動、野生動物の被害管理が専門。著書に『小学館の図鑑NEO動物(新版)』(「サル目」担当、小学館)、『里のサルとつきあうには─野生動物の被害管理』(京都大学学術出版会)、『サルはなぜ山を下りる?―野生動物との共生』(東海大学出版会)など。
※全6回終了後、有志による研修ツアーも予定しています
11月下旬~12月上旬 屋久島研修ツアー
11月下旬~12月上旬 屋久島研修ツアー アドバンストコース
1月頃 タイ研修ツアー
■問い合わせ先
〒484-0081 愛知県犬山市犬山官林26
TEL:0568-61-2327 FAX:0568-62-6823 E-mail: campus@j-monkey.jp
日本モンキーセンター「モンキーキャンパス」係
※オンラインでの手続きが難しい方はご相談ください