■ご挨拶:退任にあたって

|
公益財団として新たに発足してから、一貫してJMCを「自然への窓」と位置付けてきました。「サルを知ることはヒトを知ること」です。サルも人間も霊長類の一員であり、進化の同胞です。人間を自然と対置するのではなくその一部だと自覚します。公益財団法人としての使命のもと、尾池和夫理事長(京都造形芸術大学学長)、山極壽一博物館長(京都大学総長)、 伊谷原一動物園長(京都大学野生動物研究センター教授)とともに4人が連携した運営体制を敷いてきました。登録博物館であり動物園であり、それを公益財団として運営するという他に類例のない試みです。所長職を務めましたが無給です。京都大学教授に続いて2016年度からは特別教授という本務があり、その職責のかたわら社会貢献としてJMCに参画しました。
公益財団法人化とほぼ時を同じくして、2013年10月に、京都大学霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院(英文略称PWS)が発足しました。野生動物の研究を通じて、環境保全や動物福祉を推進する人材を育てる京都大学の大学院教育プログラムです。コーディネーターを松沢がつとめ、副コーディネーターを伊谷原一さんが担当しました。PWSの実践の場としてJMCを位置付け、動物園・博物館実習などPWS事業の一端をJMCが担いました。また京都大学が国から受託した「大型類人猿情報ネットワーク(GAIN)事業」もJMCが一翼を担っています。そうした連携を構築することで、京都大学の雇用する教職員、すなわち特定助教や特定研究員などの有期雇用教職員が、キュレーターや飼育員として日本モンキーセンターの運営や学術活動や飼育業務に参加してきました。
京大と連携することで、京大が保有するサルの調査地である幸島や屋久島や、アフリカやボルネオで、所員の多くが「生息地研修」する試みが定着しました。実際に自然の生息地で野生のサルたちとその暮らしぶりを見て、実地の体験をもとにサルの解説をします。2018年度からは上信越高原笹ヶ峰で、標高1300メートルの高原に進出してきた野生ニホンザルの研究調査も始まっています。一方、附属動物園では、飼育環境を向上させる「環境エンリッチメント」の取り組みも日々着実に進んでいます。また60年以上続く英文学術誌『Primates(プリマーテス)』の刊行を続け、季刊誌『モンキー』を復刊し、学術部の努力で『霊長類図鑑』を発刊し、学術集会である「プリマーテス研究会」を継続し、年間を通じてたくさんの学校等の生徒さんたちに来ていただいています。しかし、経営を安定した軌道に乗せる、という所長就任時に期した使命を果たすことはできませんでした。
前身の財団法人は1956年10月17日に発足しました。そこから数えると今年は64年目にあたります。旧財団時代から引き続きご支援いただいている名古屋鉄道株式会社はじめ、公益財団法人化してから新たに参画した多数の法人各位、そして1000人を超える「モンキー友の会」の皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。また、2019年3月からは女優の竹下景子さんが親善大使をお引き受けくださっています。さらにSNSを利用した情報発信やクラウドファンディングなど、若い所員の方々が自発的にくふうした新たな手法の社会連携も芽吹いています。このたび所長職を伊谷さんにお引き受けいただきました。バトンを受けてくださる次の世代の皆様が、継続する志をもって、公益財団法人日本モンキーセンターの発展にあたってくださることを願っています。末尾になりましたが、昨年末に突然始まったコロナ禍(COVID-19)と対峙しておられる皆様のご健康と、事態の速やかな終息を祈念します。
2020年3月31日
公益財団法人日本モンキーセンター所長
松沢哲郎
公益財団法人日本モンキーセンター所長
松沢哲郎
■学術誌『プリマーテス』の60年

10月17日が日本モンキーセンターの創立記念日です。その当日に祝っています。 毎年この機会にみなが集まって、動物の慰霊祭をしています。「猿塚」の前に集い、 この1年間に亡くなった者たちに思いをはせて手を合わせます。 今年は朝方は小雨でしたが、青空も見えるまでに天候が回復しました。 あらためて冥福を祈ったしだいです。
公益財団法人化した2014年以来、学校の団体利用にいっそう力を入れています。 今年の創立記念日には、たまたま坂祝(さかほぎ)小学校の2年生の生徒さんたちが来ていました。 ビジターセンターで、講師の木村直人さんの獣医の話に熱心に耳を傾けていました。可愛いですね。
1956年の創立ですが、その翌年、学術誌「PRIMATES」が創刊されました。 「プリマーテス」と読みます。学術用語で「霊長類」という意味です。 初代の編集長は今西錦司さんです。日本の霊長類学のうみの親といってよい方です。 巻頭論文も、英語で今西さんが書いています。 奥付きをみると、1957年10月25日発刊となっているので、今年で創刊60周年ということになります。 人間でいえば還暦を迎えました。
この機会に「プリマーテス」の紹介をしますね。英語の学術論文を掲載する雑誌です。 霊長類学の雑誌としては世界で一番古くから今も継続している雑誌です。 霊長類学は日本から発信してきた学問だ、ということの証拠と言えるでしょう。 いまはシュプリンガー・ネイチャーという世界的な大手の出版社から出版されています。 日本霊長類学会(現在は中道正之会長)の準機関誌と位置付けられています。
先代の編集長は山極壽一さんでした。山極さんが京大総長になられてご多忙なのでわたくしが編集長を引きついでいます。 京都大学のジム・アンダーソン教授に副編集長をお願いしています。 編集事務局には専任の職員として古賀典子さんがいます。 来年 2018年1月号から、年間4号から6号へと増加します。より強力に学問の成果を国際的に伝えたいと思っています。 次のサイトを見てください。
>>英文学術雑誌「PRIMATES」のページへ
2017年10月17日
公益財団法人日本モンキーセンター所長
松沢哲郎
公益財団法人日本モンキーセンター所長
松沢哲郎
■日本モンキーセンター創立60周年

1956年10月17日に、財団法人・日本モンキーセンターが設立された。今年、創立60周年を迎えた。 人間でいえば還暦である。2014年4月1日に公益財団法人となった。理事長は尾池和夫(京都造形芸術大学学長、京大第24代総長)、 所長は松沢哲郎(京大高等研究院特別教授)、博物館長は山極壽一 (京大第26代総長)、附属動物園長は伊谷原一(京大野生動物研究センター教授)、 学術部長は友永雅己(京大霊長類研究所教授)。それまでは名古屋鉄道株式会社が経営する日本モンキーパークの一部だった。 公益化して、動物園の部分を遊園地から切り離して独立し、京都大学の教授たちが連携して運営の主体となっている。霊長類学という学問の実践と社会貢献の場所だ。 その来し方を振り返り、行く末を考えたい。
飲水思源。井戸の水を飲むときは、井戸を掘った人のことを思いだそう。 日本モンキーセンターを創ったのは今西錦司だといって過言ではない。 新興の学問をまだ国が認知しないころ、京大の野外研究者と東大の実験医学者を糾合して民間に働きかけた。 財界で重きをなしていた渋沢敬三が仲介し、名古屋鉄道株式会社(名鉄)の当時専務でのちに社長・会長となる土川元夫が協力した。 阪急電鉄が大阪の後背地の宝塚で事業展開したのがモデルになっている。名古屋の後背地の犬山には国宝の犬山城がある。 名鉄の思惑は、そこにサル類の研究施設・博物館・動物園・遊園地を併設して、名古屋から日帰りの観光客を犬山に呼び込む。 沿線の宅地化も進み鉄道事業に資する。犬山近郊にさらに明治村を作り、リトルワールドを作った。 今西錦司と伊谷純一郎は、1958年に日本モンキーセンターを拠点として、最初のアフリカ探検に出かけた。 日本の霊長類学の興隆の歴史そのものだ。しかし1980年台を境に入園者数は下降し続けた。 存続があやぶまれた。そこで初心にかえって理想を高く掲げ、公益財団法人化という苦難の道を選んだ。
この2年半で顕著に変わったのが「生息地研修」だ。約40人の職員全員が宮崎県の幸島に行って野生ニホンザルとその暮らしを見た。 屋久島に行って、野生のシカとサルが共生する世界自然遺産の森を見た。京大熊本サンクチュアリでは、日本でそこにしかいないボノボを見た。 タンザニアやボルネオやアマゾンにもでかけた。飼育担当者だけではない。事務職員にも生息地を体験してもらった。 人々の意識をまず変えたい。実際の野外体験をもとに、自分たちの職場の掲げる理想「動物園は自然への窓」を理解してもらいたい。 キュレーターすなわち博士号をもった学芸員を増やし、さらには飼育員も修士卒業者を雇用し始めた。 京大モンキーキャンパス、京大モンキー日曜サロンというかたちで、霊長類学の成果を一般の方々にわかりやすい言葉で発信している。 その一環として、『モンキー』という雑誌を復刊した。 ただし、「霊長類学からワイルドライフサイエンスへ」と副題をつけて、霊長類だけではない、野生ウマやユキヒョウなど、 絶滅の危惧される他の動物にも焦点を当てている。 この2年間でいうと、年間約15万人が来園している。毎年200校以上の幼稚園・小学校・中学校・高校の生徒さんたちが来る。 実際にサルたちを間近で観察できる貴重な環境教育の場になっている。

モンベルというアウトドアライフの会社を創業した辰野勇さんを案内していて、カヌーを漕ぐことを思いついた。辰野さんは登山家でカヌーの激流くだりもした人だ。 リスザルの島のまわりはサルが逃げないように水濠になっている。水深は30cmほどしかない。安全だ。 パドルをそろりと操作してカヌーを漕ぎ出すと、今年4月のアマゾン川での体験をまざまざと思い出す。 木々のあいだにリスザルが見え隠れし、頭上をクモザルが渡る。 センターは約70ヘクタールの山林をもっている。モンキーバレイと呼ぶニホンザルの展示場は借景になっていて、背後に継鹿尾山(つがおさん)273mが聳えている。 その山頂の展望台から見下ろすと、センターは深い緑の中に埋まっていた。山の南斜面の林がすべてセンターの所有で、手付かずで放置されている。 尾張平野の北端の愛知と岐阜の県境の丘陵地帯だ。他人の土地をほぼ通らずに山頂までいける。「継鹿尾山自然林」と名づけて、里山の復元を試みたい。 不要な樹木を切り出すと、たき火ができる。今年の夏は「じゃぶじゃぶ池」という、水を張っただけの池で子どもたちが遊んだ。冬はたき火が良いだろう。 そもそも、センターのニホンザルはたき火にあたることで有名だ。1959年の伊勢湾台風のときに出た廃材を使った火が由緒だそうだ。 今年の冬は入園者にもたき火にあたっていただきたい。自分たちで木を集めてきてたき火をしよう。火をおこし、火にあたる。 顔や手を火照らせながら、燃える炎にじっと見入る。そうした体験を都会ではしにくくなった。サルを見るだけでなく、サルのすむ森のことを考える。 人間はその進化の過程で「野山に親しむ暮らし」をしてきた。そんな野外体験をふつうに楽しめる場所としての将来が見えてきた。

2016年10月17日
公益財団法人日本モンキーセンター所長
松沢哲郎
公益財団法人日本モンキーセンター所長
松沢哲郎
■ダンバー数:公益財団法人日本モンキーセンターからのお願い
「ダンバー数」、というのがあります。霊長類学者のロビン・ダンバーが唱えた数です。親しいと呼べるきずなをもった人の数で、だいたい150人くらいだそうです。昔ながらの暮らしをする採集狩猟民でも、現代社会のわれわれでも、その数はそう変わりません。ひとりの人間がもっている時間と、人への想いが、同じだからでしょう。
日本モンキーセンターJMCが公益財団法人化されて、ちょうど1年が経過しました。幸い、ちょうどこの1年間で、約15万人の方が入園してくださいました。約200校の幼稚園、小学校、中学校、高校の生徒さんらが団体で来てくださいました。多言語でのホームページも整い、新生JMCを目指しています。以下のホームページをご覧ください。
http://www.japanmonkeycentre.org/
公益、というのは口にするのはたやすいですが、それを実行するのは容易ではありません。それを思い知った1年でもあります。
先日の第2回「友の会」総会で講演した理事長の尾池和夫先生は無給です。半年前の第1回「友の会」総会で講演した山極壽一先生も、京大総長の激務のなか無給で博物館長を続けています。わたくしも無給で所長をしています。JMCが発行するPrimates誌の編集長もしていますが無給です。大学人の使命は、研究・教育・社会貢献ですから、それはそれで妥当だと思います。
しかし現実に約30人の職員を抱え、霊長類67種、約1000個体のサル類のいる附属動物園を運営しています。新生JMCの掲げる一丁目一番地の方針として、その職員を生息地に派遣してきました。幸島、屋久島、熊本サンクチュアリ、タンザニア、アマゾンです。それを今後も続けます。創立59年目の今年、老朽化した施設の改修も焦眉の急です。
そこで皆様にお願いです。このたび、自宅のパソコンから、お手元のカードを使ってかんたんに「寄附申込み」できるシステムを作りました。
わたくしも試してみましたが、とても簡単です。以下のサイトで、ぜひお試しいただけないでしょうか。なお、公益財団法人ですので免税措置ができます。通信欄にそのむね記載してください、証明書類を送付いたします。
https://fundexapp.jp/monkey/entry.php
みなさまのご芳志をお待ちしています。金額の多寡を問題にしていません。おひとりおひとりが寄附を試みる、その貴重なお時間とご芳志をいただけないでしょうか。また、このお願いをごく親しい方々に転送してくださって結構です。FACEBOOKやツイッターなど、SNSと呼ばれる新しい世代の方法も駆使してみてください。ダンバー数を超えた、人々の緩くて確かなネットワークが存在する。それが現代社会の特徴ではないでしょうか。新しい形の善意のひろがりを期待しています。
年度のおわりを迎えこの1年間を振り返りながら、3月31日の晩に、おひとりおひとりの顔を思い浮かべて、わたし自身もこのお願いをメイルさせていただきました。そうしてみると「ダンバー数」はなるほどという感じです。ときどきつまりながら、親類縁者、朋友、先輩、後輩、心に残る出会いの方々、そうした親しい方々のお名前を思い浮かべました。150人と、おひとりだけ故人に宛てました。天まで願いが届いて欲しいと思っています。
今後とも公益財団法人日本モンキーセンターをよろしくお願いします。
■公益財団法人日本モンキーセンターになりました

|
人間を除けば、サルのなかまは、中南米、アフリカ、インド・東南アジアに分布しています。欧米の先進国には野生のサルがいません。だから、イソップ物語やグリム童話といった西洋のお話にはサルがほとんど登場しないのです。
ニホンザルは北海道にはいません。青森県の下北半島が北限です。そして、サル類すべての北限です。熱帯の森にすむイメージなので、雪のなかにくらすサルというのは欧米人にとって驚きです。焚き火にあたるサル、とても珍しいですね。
人間を含めたサルの仲間のことを、「霊長類」と呼びます。約三百種類います。どれだけの名前をご存知でしょうか? チンパンジー、ゴリラ、テナガザル、クモザル、リスザル、ワオキツネザルなどです。じつは日本モンキーセンターの動物園は、世界でいちばんたくさんの種類のサルを飼育しています。世界一です。六七種います。実物をぜひご覧ください。
人間は人口が増えていますが、それ以外のサル類は、すべて絶滅危惧種に指定されています。自然の生息地ではその数が減っています。人間による森林伐採で生息地が破壊され、密猟もあります。サルを見ながら、ぜひ自然の暮らしを想像してみてください。
日本モンキーセンターは一九五六年にできました。この四月から、公益財団法人になりました。わたしは、隣の京都大学霊長類研究所の教員をしてきました。チンパンジーのアイたちの研究です。京大教授のまま、兼任無給で日本モンキーセンターの所長をお引き受けしています。
再来年はサル年です。そしてモンキーセンターは創立六十周年を迎えます。公益法人として生まれ変わりつつある姿をぜひ見に来てください。休園日があるのでぜひホームページを見てください。
2014年7月25日発行「成田山新聞」より
日本モンキーセンター所長・京都大学教授 松沢哲郎
■ごあいさつ
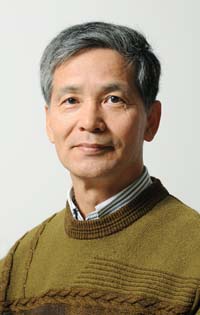 公益財団法人日本モンキセンター
公益財団法人日本モンキセンター所長、松沢哲郎 |
2014年4月1日に公益財団法人・日本モンキーセンターJMCが新たに発足しました。 新公益財団法人は、隣接する京都大学霊長類研究所や、京都にある京都大学野生動物研究センターなど、 目的を同じくする教育研究機関と連携して、霊長類の研究・調査・試資料収集・展示・学術誌発行・動物園運営・環境教育・社会貢献等をおこないます。
日本モンキーセンターは、博物館として登録されています。「サルを知ることがヒトを知ること」という視点から、人間の進化について学ぶ場所です。日本モンキーセンターには附属動物園があり、生きた霊長類の世界最大のコレクション(68種984個体、4月1日現在)を誇ります。また博物館としては、サル類の骨格等の標本11,044点を保持してその一部を公開しています。そのほかにも、霊長類学最古の国際英文学術誌「プリマーテス」(シュプリンガー社)を半世紀以上発刊しています。
このたびの公益財団法人の発足にともない、動物園を隣接する遊園地から分離しました。遊園地は引き続き名古屋鉄道の関連会社が経営し、動物園は新公益財団法人がこれを所有し経営いたします。なお休園日を設けました。週休2日です。厳冬期は休園します。サルを休ませ、環境エンリッチメントなど飼育に関連する他の業務にスタッフが励むためです。日本モンキーセンターJMCは、動物園としてはきわめて珍しいことに、全国で唯一の登録博物館です。つまり博物館であり、動物園であり、それを公益に資するものとして運営していきます。
これらの公益事業の推進のために、今回5名のキュレーター(博士学芸員、博士の学位をもつないしそれと同等の学芸員)を配置しました。さらには大学教員を常駐させる構想です。欧米の先端的な動物園に近い学術的陣容を整え、絶滅の危機に瀕する霊長類の保全や福祉の事業を進めます。
新所長にわたくし松沢哲郎(京都大学教授と兼任、無給)が就任しました。また所長の職務を補完するものとして、博物館長に山極寿一、動物園長に伊谷原一が就任しました。いずれも京大教授です。なお法令により、公益財団法人には理事の構成に制約があります。同一団体が三分の一以上を占めてはいけません。したがって一党一派に組みさない体制になっています。理事には、京大の研究者も参加し、名古屋鉄道の経営者も参加し、東大副学長などその他の機関に所属の方にも参加いただいています。理事長は、元京大総長の尾池和夫さん(現、京都造形大学長)です。
別掲の定款をぜひお読みください。
最後にお願いです。ぜひ日本モンキーセンターに足を運んでください。ホームページを見てください。新しい公益財団法人の存立はひとえに皆様のご支援にかかっています。日本モンキーセンターでお会いできるのを楽しみにしています。
・公益財団法人日本モンキーセンター 定款



営業案内
友の会
園内マップ・施設紹介
アクセス

動物園イベント
モンキー日曜サロン
ミュージアムトーク
特別展
写生大会

学習利用のご案内
団体利用・実習・研修など
モンキーキャンパス
プリマーテス研究会
おうちどうぶつえん
研究室
博物館資料
連携研究
屋久島研修所
Web霊長類図鑑
霊長類和名リスト
国際学術誌「Primates」
雑誌「モンキー」
新JMC通信
歴史・定款・年報など
スタッフ紹介
全頭誕生日カレンダー
求人情報
取材等のお問合せ
サイト利用規定
| ※日本の動物園等で飼育されている霊長類の種数は102種類です。(2015年3月31日時点、GAIN調べ。種間雑種その他の分類不明なものは除く。) |












