■京大モンキーキャンパス 記録サークルによる講演記録
京大モンキーキャンパスの受講生が、自主的に記録サークルを立ち上げました!受講生しか聞くことができない講演の様子を、サークルメンバーの視点でレポートします。
7/10(日) 「生物多様性を生み出す大元としての種分化」
西田睦 (琉球大学理事・副学長)
西田睦 (琉球大学理事・副学長)
|
霊長類の話をふだん聞き慣れているものにとって、 琉球大学副学長の西田睦先生の講義「生物多様性を生み出す大元としての種分化」は、少々とっつきにくい話だった。そのことを十分知ってか、先生は「最初はちょっと理屈っぽいですが、がまんして聞いてください」と、にこやかな笑顔で付け加えることを忘れなかった。 こちらも覚悟して耳を傾けるのだが、やはり専門用語が出てくると、そこで立ち止まってしまって、その先への足掛かりとなる想像力が膨らまない。 そして、講義の終わり、「きょうの持ち帰りメッセージは簡単にしました。『生物学の基本問題だが難題の種分化のプロセスとメカニズムの解明が、身近な生物の研究を通じて進みつつある』ということです」とスクリーンに映し出した。 種分化、適応放散、ジーンフロー・・・魚類もヒトも基本的には共通?地球に生命が誕生して間もないころから現代にいたる時間軸と、遺伝子から宇宙にまでわたる2時間の講義は、とても壮大だったが、正直歯が立たなかった。 でも、今回お許しを得て録音させてもらい、テープを巻き戻して聞いてみると、何気ない言葉の端々に、深い意味が潜んでいることの一端が、ようやく理解できるようになった。 たとえば、質疑応答の時間で出た「ヒトの進化は止まったのでしょうか?」という質問。先生はまず、「夕方にビールでも飲みながら話題にするのにいいですね」と、例によってにこやかに返したあと、「きょうは種分化や種類が増える話題をメーンにしているので、その点では、この地球上ではホモ・サピエンスが分化していくのはなかなか考えにくい」と答えられた。そして「将来、火星にあるポピュレーション(個体群)が行くかもしれないし・・」と笑いを誘った。 でも、それは冗談ではなかった。先生はその少し前、国内のアユが「地理的な分断」によって遺伝子に少しずつ違いがあることを指摘した。その「地理的な分断」を、人類が遠い将来に行くことになるとも限らない火星にまで広げ、進化や種分化の説明しようとしたのだと思う。そこで、「この地球では」とつけ加えることを忘れなかった。 魚類の話では「魚をみていると、同じ種類のオス同士はものすごいケンカをするが、ちょっと知らない種類がくると知らん顔をしている。どうして見分けがつくのか、なんとか解明したい」とも話された。一見、当たり前のようでいて、考えてみればなるほど、説明なんてできない。 |
 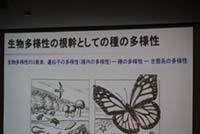 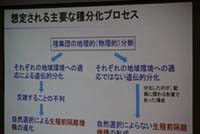
|
|
アユの研究を50年近く続けてきたという。そのアユの研究で、沖縄のアユが本土とも、大陸とも大きくかけ離れていたことを突きとめ、亜種としての学名「リュウキュウアユ」の名付け親になったことを、少しはにかんで話された。 ところが、沖縄が本土復帰するまでは豊富にいたそのアユが、復帰からわずか6年後、急激な開発によって絶滅する現場に身を持って立ち会った。絶滅に際し、みずから「最後の1匹を捕まえた」とさりげなく話されたが、長い間アユの研究してきた科学者にとって、その無念はいかばかりだったろう。 その後、奄美諸島に残ったリュウキュウアユを沖縄のダム湖に放流し、いま、少しずつ再生を図っているという。 先生は「名前をつけていて良かったなと思いました。アユのちょっと変わりモンということではなく、琉球列島に固有で貴重なものであるということになってはじめて保全の重要性が理解されるようになったのですから」と話された。 人間は言葉をもつ生き物として、「名付けることによってはじめて、その意味を認識できる」というわけだ。そう思い至って持ち帰りのメッセージの意味がはじめてわかったような気がした。「生物の種分化のプロセスとメカニズムの解明が、身近な生物を通じて進みつつある」と。ムムッ、学者おそるべし、ムベなるかな・・。 文・写真 : 京大モンキーキャンパス受講生 柴田永治
|



営業案内
友の会
園内マップ・施設紹介
アクセス

動物園イベント
モンキー日曜サロン
ミュージアムトーク
特別展
写生大会

学習利用のご案内
団体利用・実習・研修など
モンキーキャンパス
プリマーテス研究会
おうちどうぶつえん
研究室
博物館資料
連携研究
屋久島研修所
Web霊長類図鑑
霊長類和名リスト
国際学術誌「Primates」
雑誌「モンキー」
新JMC通信
歴史・定款・年報など
スタッフ紹介
全頭誕生日カレンダー
求人情報
取材等のお問合せ
サイト利用規定
| ※日本の動物園等で飼育されている霊長類の種数は102種類です。(2015年3月31日時点、GAIN調べ。種間雑種その他の分類不明なものは除く。) |












