■京大モンキーキャンパス 記録サークルによる講演記録
京大モンキーキャンパスの受講生が、自主的に記録サークルを立ち上げました!受講生しか聞くことができない講演の様子を、サークルメンバーの視点でレポートします。
10/9(日)「動物たちの心の世界」
友永雅己(公益財団法人日本モンキーセンター学術部長・京都大学霊長類研究所教授)
友永雅己(公益財団法人日本モンキーセンター学術部長・京都大学霊長類研究所教授)
| 《講義抜粋》 比較認知科学は「こころはいかに進化してきたのか」を探求する学問で、これまで社会的環境に重点を置いて研究されてきたが、友永氏は生態環境や物理的な環境も大切であると説く。高い樹上でも生活するチンパンジーは、その身体能力ばかりでなく、そうした環境の中で認識する能力が長い時間をかけてチンパンジーの「こころ」をなしてきたからだと説く。そうした視点から、霊長類学者としてここ近年、霊長類にとどまらず、ウマやイルカ、ヤギやリクガメにまで研究対象を広げ、相対化したこころの動きという視点から比較認知科学を見直している。 |
|
友永先生の講義は、いっけん簡単そうに見えて、実はとても難解でした。というのも、「こころの動きの相対化」という、私自身はこれまで、ちょっと考えてもみなかったことを、先生はどうやら本気で研究されようとしていることに理解が及ばなかったからだと思います。 霊長類学者が馬やイルカの研究にたどり着くのはともかくとして、モンキーセンターにいるヤギやリクガメにまで手を広げて研究対象とするというのは、講義の中でのちょっとした冗談か、はたまたリップサービスなのかと思っていました。ですがどうやら、先生は本気のようなのです。そこのところを、しっかり押さえていなかったばかりに、先生の講義はとっても難解になってしまったのだと、いまさらながら思うのです。 そのことに気づいたのは、復刊された「モンキー」2号で先生がお書きになった「チンパンジー、イルカ、そしてウマからみた世界」に目を通してからです。先生はこのようにお書きになっています。 比較認知科学とは「こころはいかに進化してきたのか」を探求する学問で、「生き物が環境に適応してきた結果として進化してきた」というのですが、友永先生はこの四半世紀ほど強調されてきた社会的環境の重要性に対して、「生態環境や物理的な環境もけっこう大事なのではないかと思い始めている」というのです。 その一例として、霊長類研究所にいるチンパンジーは15mの高さに張られたロープを二足立ちで軽々と移動しますが、「そこで発揮されている身体能力や環境を認識する能力(つまりこころ)は、とてもユニークである。森林という環境がそのユニークな心を作ったのだ」と指摘されます。 また、超音波を発信してその反響の強弱や返ってくる時間で世界を見ているイルカは、実はとても視力が弱いのだそうですが、そのイルカが視覚に頼って世界を見ようとすると、人やチンパンジーが見るのと同じような「かたち」が目の前に広がっていることを研究を通じて知ったそうです。そして先生は、「これは私にとっては新鮮な驚きでもあった」と述懐しています。 これまた、講義のなかで「ちょっと、冗談か」と思っていた「ウマ目線」や「イルカ目線」についても、先生は本気で探求されているのだと思います。そして、「異なる世界に適応していても、『見た世界』のエッセンスはほ乳類の間ではとてもよく似ているのかもしれない。問題は、その世界からの情報をどのように解釈しているか、という『認知』にあるのだろう」と述べています。 |
  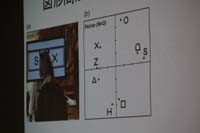 |
|
文 : 京大モンキーキャンパス受講生 柴田永治
|



営業案内
友の会
園内マップ・施設紹介
アクセス

動物園イベント
モンキー日曜サロン
ミュージアムトーク
特別展
写生大会

学習利用のご案内
団体利用・実習・研修など
モンキーキャンパス
プリマーテス研究会
おうちどうぶつえん
研究室
博物館資料
連携研究
屋久島研修所
Web霊長類図鑑
霊長類和名リスト
国際学術誌「Primates」
雑誌「モンキー」
新JMC通信
歴史・定款・年報など
スタッフ紹介
全頭誕生日カレンダー
求人情報
取材等のお問合せ
サイト利用規定
| ※日本の動物園等で飼育されている霊長類の種数は102種類です。(2015年3月31日時点、GAIN調べ。種間雑種その他の分類不明なものは除く。) |












