■京大モンキーキャンパス 記録サークルによる講演記録
京大モンキーキャンパスの受講生が、自主的に記録サークルを立ち上げました!受講生しか聞くことができない講演の様子を、サークルメンバーの視点でレポートします。
6/11(日)「霊長類の新常識:個性的なテングザルを追って」
松田一希(中部大学創発学術院 准教授)
松田一希(中部大学創発学術院 准教授)
|
半年ぶりの京大モンキーキャンパス再開。
しょっぱなは、テングザル研究の第一人者で、若くて背も高い松田一希先生です。
どんな講義になるのか、会場はいつもの雰囲気とはやや違い、受講生、特におばさま族(失礼!)のみなさんからはどこか熱い視線も。
お目当てだったテングザルの長く伸びた鼻の話は時間切れということで次回以降に持ち越されましたが、
先生がたどった研究への糸口は、興味津々の受講生を引きつけたのでした。 開口一番、松田先生は「テングザルの研究を12年やっているが、もともと大学の工学部でセラミックスの研究をしていました」と意外なことおっしゃいます。 ジェットエンジンのヒーターの研究で、毎日、金属をこねて焼き、硬さを調べていたそうです。 で、霊長類の研究をすることになったきっかけが笑わせてくれます。 たまたま隣がクモザルの研究室で、廊下でよく顔を合わる研究室の先生からある日、「君、アマゾンに来ないか?」と突然誘われたそうなのです。 「面白そうだ」と行ってみた南米コロンビアのジャングルは、毎日毎日が新しい発見の連続。 クモザルの朝のロングコールや、小集団になると見つけるのも難しいといわれるクモザルが、「この辺にいるんじゃないか」と思うとなぜか、その通りに見つかる。 きわめつけは、目の前2~3㍍のところで、何と体長2メートルもあるジャガーにクモザルが襲われて食べられるところまで見てしまったというのです。 「君には動物運がある」と先生にほめられ、すっかりその気になってしまったのが、180度転身するきっかけだったようです。 それからもまた面白い!!大学院に進んだものの、政情不安のコロンビアに行けなくなり、研究を続けられなくなった先生が、ある日たまたまNHKのテレビを見ます。 すると、ボルネオの密林でテングザルが15メートルもの高さから次々、川に向けてダイビングする姿を見たのでした。 最初の1、2頭が川に飛び込むと、それからは10頭あまりものテングザルが水をものともせず、次々に大ジャンプを繰り広げる。 モンキーセンターで見ていると、「サルは水を怖がるもの」とばかり思っていた先入観が、テレビに映し出された映像でもろくも消え去りました。 |
 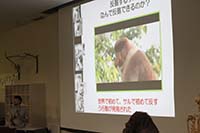  |
|
当時、北大大学院の博士課程で、アマゾンから研究拠点を変えざるを得なくなっていた先生は「とりあえずボルネオに行ってみよう、行けば何とかなる」と、
片道チケットで出発します。博士課程ともなると、綿密な研究計画を立てからフィールドへ出発するのが普通とのことですが、先生は「1年見ていれば生態が明らかになるだろう」と思ったそうです。
いまの学生からそんなことを言われたら、松田先生でも「『もう少し考えたら』とアドバイスするでしょう」と苦笑するのですが、その時の指導の先生もまたすごい。
「行って来い」と背中を押したというのです。 さて、現地での1年の滞在期間中、3506時間もの観察記録を残しました。1日換算でざっと150日分。長大な観察記録を冗談めかしてお話されたのは、「休んでいた」70%、「食べていた」20%という彼らの何とものどかな暮らしぶりです。 しかし、徐々に秘密のベールに包まれたテングザルの生態が明らかになっていきます。その最大のものは、彼らが川沿いで生活し、しかも、川岸から800メートル以上は離れないということだったといいます。 発見そのものの意味が当時わからず、「へえ?、ということぐらいだった」といいます。しかし、アブラヤシのプランテーションがどんどん広がって森を侵食していくいま、この800メートルという数字はテングザルの生息域を確保するうえで極めて重要な意味を持っているといいます。(このアブラヤシ、サラダ油から化粧品までわたしたちのあらゆる日常生活でお世話になっています) さて、そんな楽しいお話から次第に本題に入っていきます。 先生が特に注目したのは彼らの社会構造です。そして、彼らの暮らしがオス中心のハーレム社会なのに、あぶれたオスグループとはケンカをほとんどしない。また、チンパンジーのように他の群れとの間でオス同士の殺し合いもしない。時には同じ1本の木でハーレム同士が別々に寝たりする奇妙な生態に気づきます。 それは、彼らがわれわれ人間社会と同じように、複雑な重層社会を持っていることともつながることなのですが、それがなぜなのかを、まだまだ十分明らかになっていないテングザルの生態から、仮説も交えて講義していきます。 そこでヒントとなるのは乾燥地帯で暮らすゲラダヒヒや、中国南部の高山で暮らすキンシコウなど、同じ重層社会を持つサルたちとの比較です。水や食べ物も十分でない場所で暮らすヒヒやキンシコウたちは、厳しい環境を乗り越えるために、ハーレム型のコアユニット(最小の集まり)で離合集散を繰り返しながら生活します。さらに、ほかのオスグループからハーレムを奪われたり、より大きな動物から捕食されたりする圧力に絶えず受けている。 しかし、熱帯林に暮らすテングザルが、ハーレムを維持しながらも、食べ物が少なくなった時期はコアユニットになって離合集散を繰り返す姿を見ながら、「テングザルの離合集散は、環境要因であるていど説明できるのではないか」と考えます。 そして、彼らが母系なのか父系なのか、どのような社会基盤を持っているかという根本的な問題については、父系社会ではないかと推測します。その根拠として、先にみたオスグループからのハーレムへの攻撃が弱い点をとらえ、実は、ハーレムの子供たちが他のオスグループとも血縁関係があるからではないかと推測します。 さらに、テングザルの社会で子殺しがない点についてもその根拠の一つにあげます。つまり子殺しは、みずからがハーレムの核オスとなって、メスの性周期を取り戻させて自分の子孫を残すための行為と考えられるのですが、テングザルの社会では、生まれたばかりの子を持つメスザルですら、核オスがハーレムに受け入れるといいます。それらの点は、彼らの社会が「父系社会であると考えれば納得がいく」と説明されるのです。 やれやれ、門外漢にとっては、そうした仮説や推測がどのような意味合いを持つのかが、いま一つピンと来ない部分もあったのですが、専門家の間では、いまもかなりの議論になっていることだけは推察できます。 実はテングザルの胃袋は四つに分かれ、ウシやヒツジたちのように反芻をしているそうですが、この反芻が認められるまで5年もかかったというのですから・・・。 そうした確証を得るために、先生はテングザルの夜間の行動観察にも挑みます。赤外線カメラを使って夜通し撮影し、テングザルたちは夜間に寝ているのは実は半分ほどで、あとしょっちゅう目をキョロキョロさせたり、オス同士で鳴き交わしたりしている生態を明らかにしていきます。 しかし、この観察は大変なようです。なにせ、真夜中から朝までたっぷりとカメラを回し、日本に帰ってからこのビデオを再び見直さなければならないというのですから。 2010年からこうした観察を始め、これまで2000時間を撮影しても、反芻が確認できたのは11回!!!まだまだナゾの多いテングザルの生態はこうした努力で徐々に明らかになっていきます。 最後に先生は「これだけは」と、テングザルの頭部をCT検査した貴重な写真を見せてくれました。そこには、同じ仲間のほかのコロブス類となんら変わりのない頭部の写真があるだけでした。 鼻が長いとモテるというテングザルの鼻は、では、どのように伸びるようになったのでしょう?(男性陣としてはついでに“鼻の下”の長さも計ってほしい(> <))。肝心カナメのお話は次回以降にということで、実に気を持たせてくれる2時間でした。 文 : 京大モンキーキャンパス受講生 柴田永治
|



営業案内
友の会
園内マップ・施設紹介
アクセス

動物園イベント
モンキー日曜サロン
ミュージアムトーク
特別展
写生大会

学習利用のご案内
団体利用・実習・研修など
モンキーキャンパス
プリマーテス研究会
おうちどうぶつえん
研究室
博物館資料
連携研究
屋久島研修所
Web霊長類図鑑
霊長類和名リスト
国際学術誌「Primates」
雑誌「モンキー」
新JMC通信
歴史・定款・年報など
スタッフ紹介
全頭誕生日カレンダー
求人情報
取材等のお問合せ
サイト利用規定
| ※日本の動物園等で飼育されている霊長類の種数は102種類です。(2015年3月31日時点、GAIN調べ。種間雑種その他の分類不明なものは除く。) |












